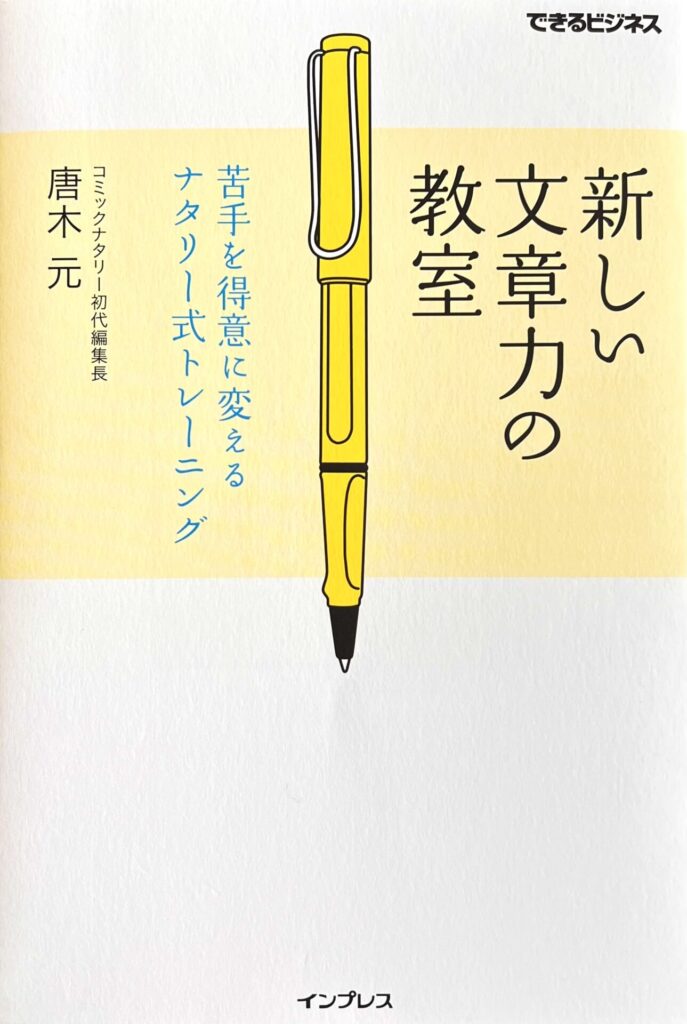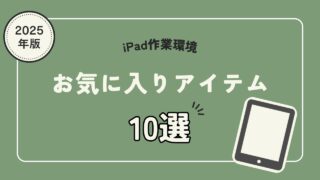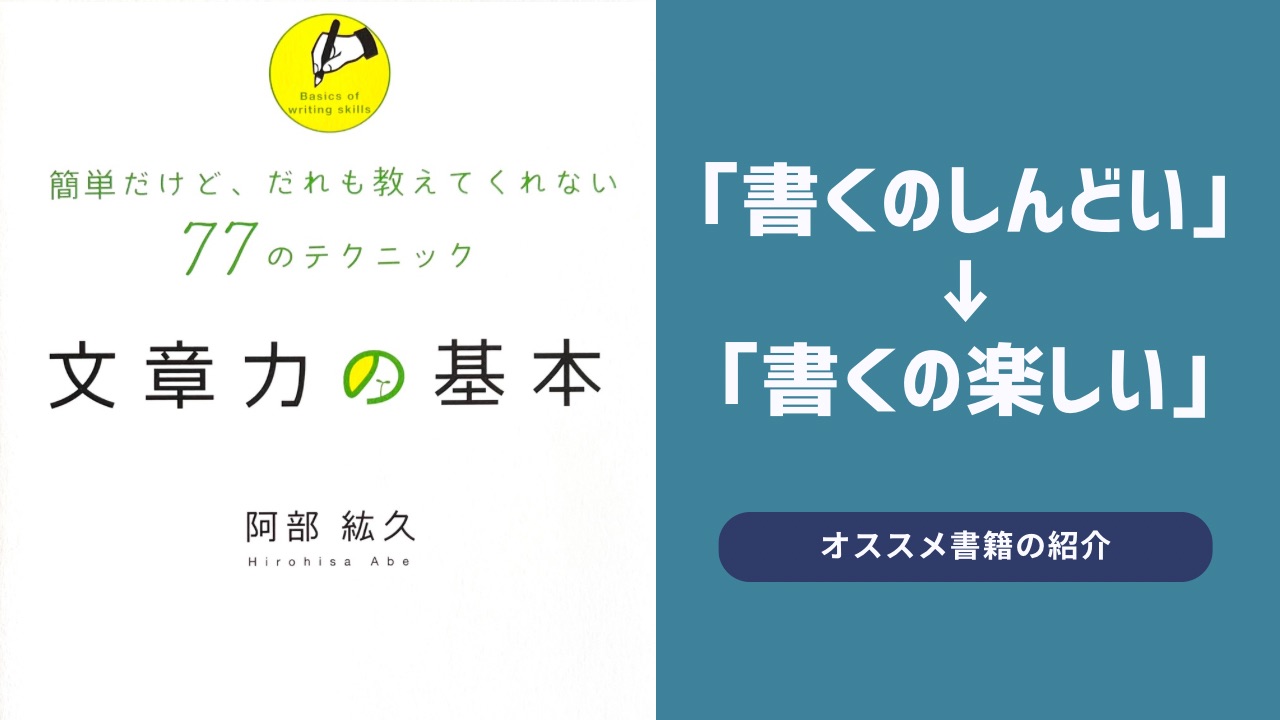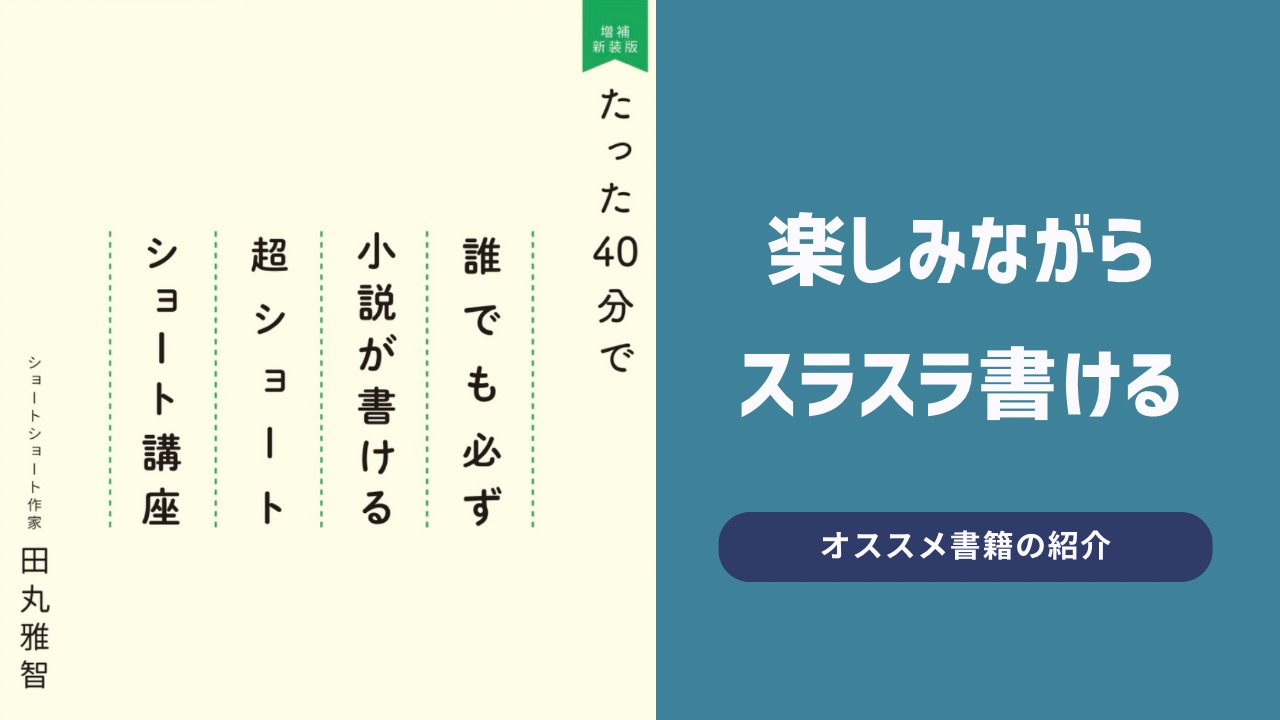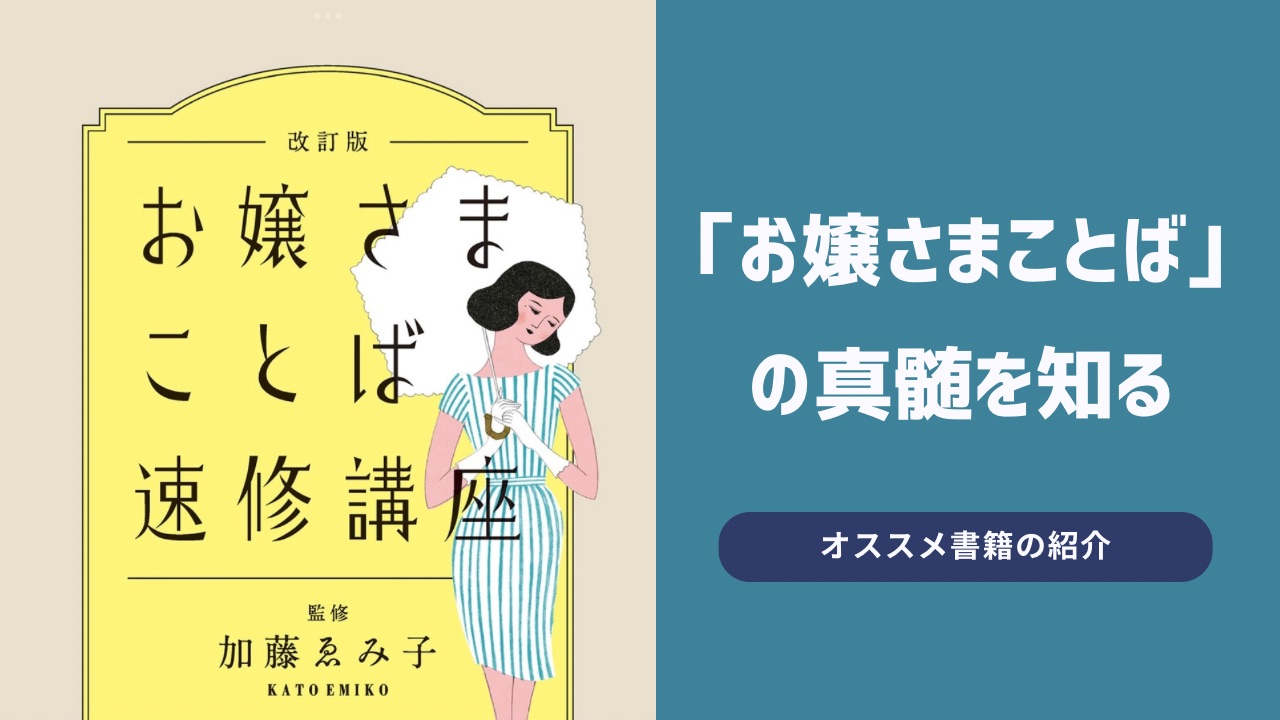「書けない」私にヒントをくれた文章術の本『新しい文章力の教室 苦手を得意に変えるナタリー式トレーニング』|小説執筆への活かし方
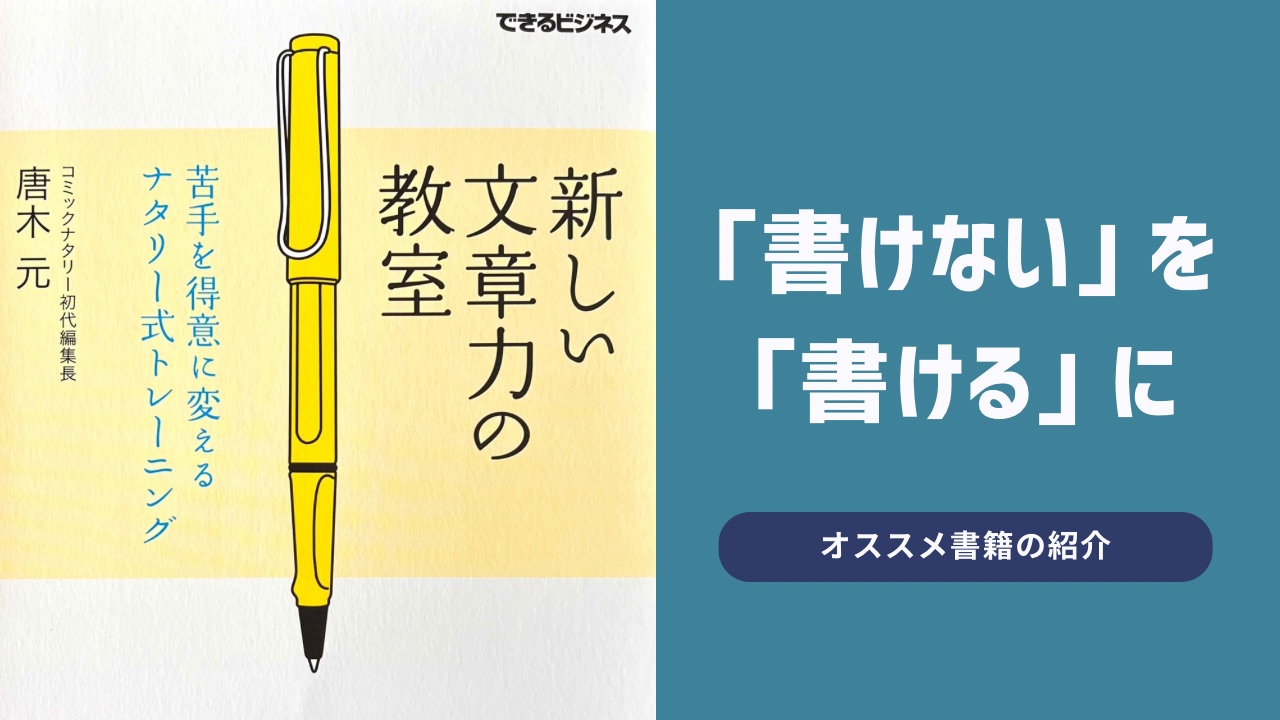

書きたいことはあるのにうまく書けないし途中まで書けても最後まで辿りつかない……!!
↑これは以前の私です。毎回ヒーヒー言いながら、1から文章を絞り出して小説書いていました。
まあ、だから〆切に間に合わなくて新刊を落とすんですよねぇ……(遠い目)
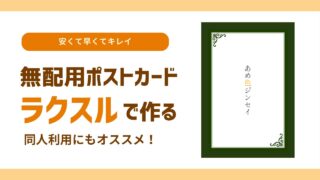
文章を書くこと自体は好きだし、書きたいこともあるんだけど、書けない。このジレンマは結構こたえます。
自分には小説が書けないんじゃないか、向いていないんじゃないか、なんて思ったこともありました。
でも先日『新しい文章力の教室 苦手を得意に変えるナタリー式トレーニング』という本を読んで気づきました。

書けない原因は向き不向きではなくて、書き方だった!
「書きたいことがあるのに書けない」のは、「書きたいこと」が整理されていないからでした。
情報を整理してプロットを書き、それをもとに肉付けしていったら、すんなり文章を書き上げられました。
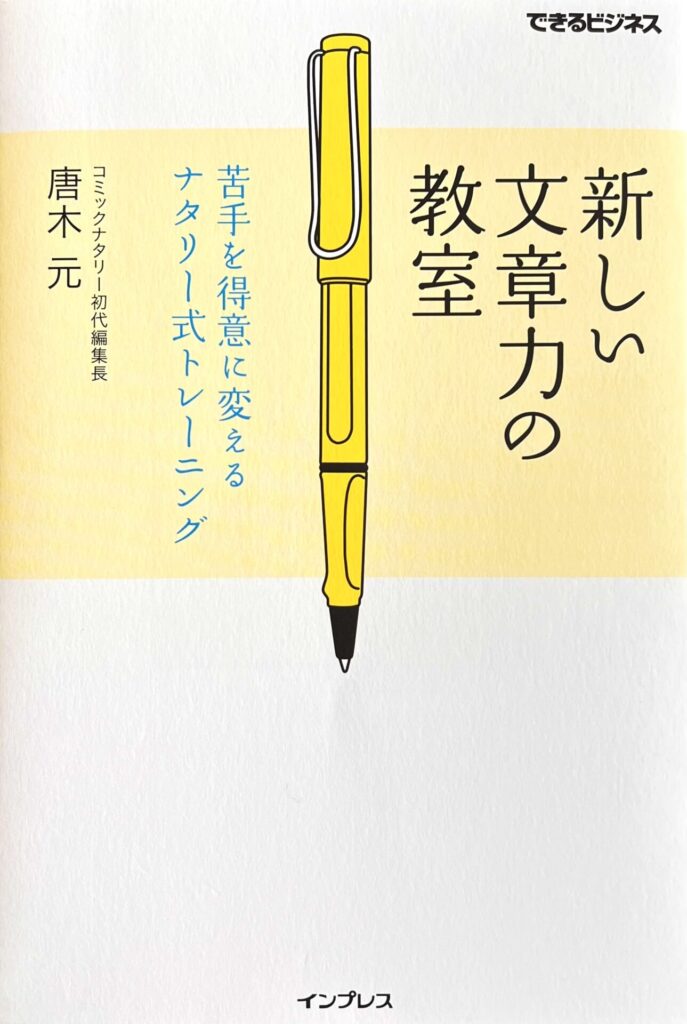
著者はネットメディアであるコミックナタリーの初代編集長、唐木元さん。
この本は、社内で「唐木ゼミ」と呼ばれる新人社員向けのトレーニングから「書くこと」についてまとめたものです。
これを読んでいるあなたが、「書きたいことがあるけどどう書いたらいいかわからない」というステイタスにあるのだとしたら、
〜中略〜
私がこれまでに培ってきたメソッドがきっとお役に立てると確信しています。それはひと言で言えば、「いきなり書き始めてはいけない」というシンプルな話。書き始める前に、何について書くか決めてから書く。さらには何をどれから、どれくらい書くかを見当付けてから書き始める。たったそれだけのことが、唐木ゼミの核心です。
この本はナタリーの記者に向けたトレーニングがもとになっているため、小説を書くための指南書ではありません。
でも、「アイデアはあるけどうまく書けない、書ききれない」人向けの本なので、私のように書けなくて(最後まで書ききれなくて)困っている人には参考になると思います。
ただ、読んでいる中で少しだけ気になる点もありました。

「言っていることはわかるけど表現があまり好きじゃないかも」と感じる部分が多々あり……
「言葉づかい」について解説する章で特に感じられました。これは私が実用書を読み慣れていないせいと、単に私の好みの問題だと思います。
気になったのはそのくらいでした。
手法を真似たら書き方の改善につながったので、この本は読んで良かったです。
『新しい文章力の教科書 苦手を得意に変えるナタリー式トレーニング』を読んで参考になった部分をピックアップし、
- 小説にどう活かすか
- 小説に置き換えるとどう考えられるか
という観点での私なりの解釈をまとめました。
手順に沿って文章を書く過程も載せています。
「書けない」と悩んでいる人の参考になると嬉しいです。
まずは文章の3層構造を理解する
文章の構造は、下から順に
- 事実:根幹・土台
- ロジック:論理
- 言葉づかい:表層・伝達手段
が積み上がってできている。
文章の構造って、考えたことありますか?
私は今まで「言葉づかい」を磨くことばかりに気を向けていて、文章の構造なんて考えもしなかったです。

これって小説でも当てはまるの?
ということで、考えてみました。
フィクションであったとしても、その世界の中で起きている事実は必ずあります。
いくら綺麗な言葉や難しい言葉が使えたとしても、肝心なストーリーが破綻してしまっては読み物として成り立ちません。
なので小説執筆に置き換えて考えてもこの3層構造は当てはまると考えました。
「事実」で固めた土台の上に「ロジック」を重ねて文章を書くこと、推敲の段階になってから「言葉づかい」で表現力を発揮することが重要なんだと思いました。

文章の3層構造は文章の基本形。小説を書く際も意識する!
書く前に「書くもの」の準備をする
- 「良い文章とは何か」を定める
- 主眼と骨子を決めておく
「良い文章とは何か」を定める
筆者は「わかりやすい」「テンポがいい」「元気が出る」など、いろんな意見をひっくるめて
「良い文章」とは「完読される文章」である
としています。
小説に置き換えて考えても、最後まで読まれなければ物語が中途半端な状態で終わってしまうし、作者が用意したエンディングまで到達せずに終わってしまいます。
長編も短編も掌編も、詩や短歌も、あらゆる文章は最後まで読まれなければ伝えられないし、感じてもらえない。
ということは、「小説における良い文章」も「完読される文章」と言えると思いました。
私が心に刻んでいる「小説における良い文章」の定義は
「簡単な言葉だけで感情を揺さぶってくる文章」
なんですが、これも結局のところ読まれないと意味がないので詰まるところ「完読される文章」ってことになりますね。

小説でも「良い文章」=「完読される文章」と言える!
主眼と骨子を決めておく
- 主眼=テーマ・コンセプト
- その文章で何を言うのか、何を言うための文章なのかという目的
- 骨子=骨組み
- 「要素」「順番」「軽重」から成る
文章の3構造(「事実」「ロジック」「言葉づかい」)に照らし合わせると
- 「要素」=「事実」
- 「順番」「軽重」=「ロジック」
に当てはまります。

つまりどういうこと……?
つまり書き始める前にテーマを決めて「何を(要素)」「どれから(順番)」「どれくらい(軽重)」書くか決める、ということ。
これが「書けない」を「書ける」にするための最重要ポイント。私に圧倒的に足りていなかったのは才能でも語彙でもなく、この下準備でした。
本書ではプラモデルに例えられていました。
プラモデルのように作文する
「どんなことを伝える文章なのか」を定めておく(箱絵)、「何を言うか」をトピック化して並べておく(パーツ)、「どこから」「どこを重点に」組み立てるかを決めておく(取説)。
〜中略〜
つまり、「箱絵=主眼」「パーツ=要素」「取説=順番・軽重」という具合です。
「書き始める前に主眼と骨子を決めておく」とは、言い換えれば「作文をプラモ化しておく」ということなのでした。
いかに文章が「事実」と「ロジック」で成り立っているかがわかります。
手の届くところにパーツがないのなら、取説を持っていてもプラモデルは作れないですよね。
パーツを探して、組み立てて、パーツを探して、組み立てて……そんな繰り返しでは途中で嫌にもなります。
ざっくりした内容を頭に思い浮かべただけで書き始めるから、最初の1行でつまづいたり、続きをどうしようか悩んで手が止まってしまうのでした。
試しに小説を書いてみる

実際のところ小説を書くときはどうしたらいい?
という疑問が出てきたので、ここからは試しにサンプル小説を書いていきます。
本の手順に沿って主眼と骨子を決めていきます。
「要素」=「事実」、プラモデルに当てはめると「パーツ」のことでした。
この集めた要素を
- 箇条書きで書き出すこと
- 5W1Hに当てはめて足りない情報を補うこと
が指示されています。
「5W1H」は英語のWho(誰が)、What(何を)、When(いつ)、Where(どこで)、Why(なぜ)、How(どうやって)を頭文字の数で表したものです。
小説で考えるとこんな感じでしょうか。
- 女の子2人の夢語り
- 中学生で卒業間近
- 幼馴染
これを5W1Hに当てはめてみます。
- Who(誰が)、What(何を)
- 女子中学生の幼馴染2人が夢を語る
- When(いつ)
- 自分たちの卒業式の前日
- Where(どこで)
- ?
- Why(なぜ)
- ?
- How(どうやって)
- ?
Where、Why、Howが抜けていることがわかりました。
要素を付け足します。
- Who(誰が)、What(何を)
- 女子中学生の幼馴染2人が夢を語る
- When(いつ)
- 自分たちの卒業式の前日
- Where(どこで)
- 市内で一番の高台にある展望台
- Why(なぜ)、How(どうやって)
- 小学生の頃から2人で自転車で坂を登りきるチャレンジをしていた
要素がすべて埋まりました。

こうやって改めてみると、要素を書き出すことの重要性がよくわかりますね。
本文を書き始める前に、「主眼」を設定します。
主眼とはテーマ・コンセプトのことであり、その文章で何を言うのか・何を言うための文章なのかという目的のこと。
プラモデルに当てはめると「主眼」=「箱絵」でした。
このお話で何を描きたいのかを決めます。
要素を確認します。
- 女子中学生の幼馴染2人が夢を語る
- 自分たちの卒業式の前日
- 市内で一番の高台にある展望台
- 小学生の頃から2人で自転車で坂を登りきるチャレンジをしていた
主眼はこんな感じでしょうか。
小学生の頃からのチャレンジを達成した中学卒業前日、幼馴染2人が語る将来に対する展望
形になりました。
あおり文としても使えそうですね。
あおり文とは?
本の帯などに書かれる宣伝文句。購入意欲を煽るための文章。

あおり文として使える主眼を決めると、このお話で何を描きたいのかという軸がブレない!
次は「ロジック」の中の「順番」。
プラモデルで言えば「取説の手順」を決める段階です。
主眼と要素を確認します。
主眼
小学生の頃からのチャレンジを達成した中学卒業前日、幼馴染2人が語る将来に対する展望
要素
- 女子中学生の幼馴染2人が夢を語る
- 自分たちの卒業式の前日
- 市内で一番の高台にある展望台
- 小学生の頃から2人で自転車で坂を登りきるチャレンジをしていた
書く順番を決めます。
- 市内で一番の高台にある展望台
- 小学生の頃から2人で自転車で坂を上りきるチャレンジをしていた
- 女子中学生の幼馴染2人が夢を語る
- 自分たちの卒業式の前日
卒業式前日だということを一番最後におき、2人がなぜこんなに夢を語るのかを想像させる展開にしてみました。

何度も順番を変えてみて、しっくりくる展開を探る!
最後は「ロジック」の中の「軽重」。プラモデルで言えば「取説の重要度」です。
本書にはABCの3段階評価で見定めるとありました。
同じようにABCで割り振ってみます。
- 市内で一番の高台にある展望台:B
- 小学生の頃から2人で自転車で坂を上りきるチャレンジをしていた:B
- 女子中学生の幼馴染2人が夢を語る:A
- 自分たちの卒業式の前日:C
卒業式の前日である、ということは最後に付け足せればいいのでC、一番のメインである夢語りをA、他をBにしました。
これで主眼と骨子を決める作業は終了。
書き出すことで、頭の中のフワッとしたアイデアが整理されていきました。
この段階で足りない要素を補えるのは大きいです。
これならそうそう文章迷子にならないなと思いました。

事前準備をするかしないかが、書ききれるか否かの分かれ道!
プロットを書いて整理する
主眼・骨子を1枚の紙などにまとめます。本書ではこれを「構造シート」と呼んでいました。
小説で言えばプロットにあたるものですね。
手書きをする
「最初からPCでやると、主眼と骨子を考えずにいきなり本文を書くやり方に戻ってしまうから手書き推奨」ということでした。
- A4コピー用紙
- ノート
など、なんでもOK
コピー用紙でもノートでもいいとありますが、中には「紙に書くのはちょっと……」という人もいますよね。かく言う私自身がそうです。
そういう人は紙ではなくiPad(タブレット)で手書きするのがいいと思います。
「手書きで」とは言っていますが「紙に」とは言っていないので、手書きできるならなんでもいいのだと思います。
もしくは「絶対にプロット作ってから書く」と決意して打ち込みにするとか。
いずれにせよ、ストレスの溜まらないやり方がいいですね。

私は純正メモアプリに書いています
順番を変えるときは毎回書き直す
書き直すことで全体が把握できるので、流れの悪いところがわかりやすくなります。
これは番号を振り直すだけだと効果を得られないそう。なので、順番通りに書き直すことが大切です。
主眼と照らし合わせて要素を取捨選択する
この段階で
- テーマからズレているもの
- 絶対に必要と言えないもの
は潔くカット。
厳選して要素を出しているのでカットするものはほとんどないですが、常に疑いの目を持つことは大事ですね。
肉付けしながら本文を書く
いよいよ本文を書き始めます。
とその前に、主眼と骨子を改めて確認します。
主眼
小学生の頃からのチャレンジを達成した中学卒業前日、幼馴染2人が語る将来に対する展望
骨子(要素・順番・軽重)
- 市内で一番の高台にある展望台:B
- 小学生の頃から2人で自転車で坂を上りきるチャレンジをしていた:B
- 女子中学生の幼馴染2人が夢を語る:A
- 自分たちの卒業式の前日:C
要素をつなげて簡単な文章にする
要素をつなげると簡単な文章になります。
小説なので視点決めが必要ですね。今回は一人称でいくことにします。
要素の文言をちょっとだけ変えてつなげてみたものがコチラ↓
市内で一番の高台にある展望台。小学生の頃からずっとこの急坂を上り続けてきた。あの子と私、自転車で。
展望台で街を見ながら幼馴染の夢を聞き、私の夢を語る。
私たちは明日、中学校を卒業する。
本書の中では、「言葉はつたなくとも言いたいことは伝わる文章になる」とありました。
出来栄えはひとまず置いといて、確かに読める文章にはなっています。
「軽重」を意識しながら文章を足す:小説の形にする
要素をつなげただけの文章に、「軽重」を意識しながら文章を足していきます。
市内で一番の高台にある展望台。そこを目指して、小学生の頃からずっとこの急坂を上り続けてきた。あの子と私、自転車で。
視界が開け、風が吹き抜けた先で対面した展望台は、車で来た時と全く違って見えた。
最後の力を振り絞って展望台の階段を上り、てっぺんでベンチに座り込む。
眼下に広がる街。住み慣れた街が、なんだか知らない場所のように見えた。
「こんなに達成感があるとは思わなかったなー」
伸びをしながら彼女が言った。
中学生でやっと、長いチャレンジが終わりを迎えた。いざ終わってみると晴れやかで誇らしいような、哀しいような、複雑な気持ちだ。
そういえば、終わった後はどうするかという話をしたことがなかった。
「これからどうしようか」
「私ね、やりたいことがあるんだ」
「なに?」
「ふふん、聞いて驚かないでよね!」
「それは聞いてみないとわかんないけど」
彼女がキラキラした瞳で語る新しい夢は、私をワクワクさせた。
この自転車チャレンジをやろうと言い出したのも彼女だった。
彼女はいつも私のことをワクワクさせてくれる。そしていつの間にか、私にも新しい夢が生まれているのだ。
展望台で街を見ながら幼馴染の夢を聞き、そして私の夢を語る。
いつまで続くのかわからない、心地よい2人だけの時間。
私たちは明日、中学校を卒業する。
言葉づかいを意識せず書いているので荒削りではありますが、小説の形になりました。
二次創作であればキャラクターを1から作る必要がないので、この方法だけでお話が書けますね。
ショートショートなどもこの手順だけで書けそうです。
完成度が低くてもまずは最後まで書ききることが大切
世に出ない傑作よりも読める佳作を目指す気持ちで書いたら、「とりあえずここはこのままでいいや」と気持ちを切り替えて先に進むことができました。
気になるところは推敲時に修正すればいいんですよね。
推敲の時間を捻出するためにも、まずは書ききることが大切だと感じました。
文字数が多い文章を書くときは、パート分けしてそれぞれにプロットを作る
章ごとにプロットを作れば「もうなんだかわけわからん」という文章迷子にならずに済みます。
プロットを見返して、必要があれば噛み砕く作業をすると良さそうです。
今回サンプルとして書いたお話も、文字数を増やすならパート分けしてプロットを作った方がいいなと思いました。そうしないと手が止まりそうです。
最後まで書けても終わりじゃない|推敲して言葉に磨きをかけていく
本文が最後まで書けたら終わり! ではなくて、書けるようになったら推敲が待っています。
ここからがメディアと文芸の分かれ道だと私は思います。
本で紹介されていたテクニックの中から、「小説を書くときにも心がけよう」と思ったことをまとめてみました。
- 適切なスピード感のコントロール
- 自分が理解していない言葉を書かない
- 具体的な言葉に置き換える
- 手癖で同じような文章にならないよう、どこかしらに変化をつける気持ちを忘れない
適切なスピード感のコントロール
文字数あたりの情報量のこと
無意味に長い文章だと途中で読むのをやめてしまうし、必要以上に短く切られる文章ばかりだとそっけなくて読む気がしなくなるもの。
一辺倒ではなく、シーンに合わせたコントロールが必要。
自分が理解していない言葉を書かない
「なんかこんな意味だった気がする」というあいまいな状態で言葉を使わないこと。
人に聞かれて正しく答えられないなら調べる。

私は言葉の使い方を間違えたまま表に出してしまったことが何度もあります。
あまりにも恥ずかしくて調べる癖がつきました(それでもまだゼロにならないので意識して調べるようにしています)
具体的な言葉に置き換える
周りくどい書き方をするよりもストレートに書いたほうが伝わることがある。
必要があれば説明文も添える。
手癖で同じような文章にならないよう、どこかしらに変化をつける気持ちを忘れない
類語辞典などで言葉、文章の幅を広げると、「前もこんな感じの文章書いたな」ということが減る。
過去に書いたものを読み返して自分の癖を確認し、意識的に変化をつける。
さいごに
「書きたいことはあるのにうまく書けないし途中まで書けても最後まで辿りつかない」と悩んでいました。
『新しい文章力の教科書 苦手を得意に変えるナタリー式トレーニング』を読んだことで
- 要素を書き出すこと
- プロットを作成すること
の重要性に気づき、「書けないループ」から脱することができました。
今は主眼と骨子を書き出してから肉付けするようになったので、「全く書けない」ということはありません。
まずは最後まで書ききるということにも抵抗がなくなり、文章を書くのが楽しくなりました。
そして不思議なことに、随分とスッキリした文章になったのに今まで以上に反応がもらえたのです。
少なくとも前よりも読まれる文章になったということだと思います。
「プロットを書くとそれで満足してしまうからプロット書かないでいきなり本文を書き始める」というプロット不要派もいますが、誰もがそうではないです。
現に、私にはプロットが必要でした。(実は不要だと思っていました。自分じゃわからないものですね)
- 小説を書き始めたばかり
- アイデアはあるけどうまく書けない、書ききれない
という人は、先にアイデアを整理してみるとスラスラ書けるようになるかもしれません。
「小説の書き方」みたいなド直球な本以外は参考にならないのかと思いきや、実用書の文章術も活かせることがあり、面白かったです。
考えてみれば「日本語の文章を書く」と言う点は共通しているし、全く無意味なことはないなと思いました。何事も思い込みはよくないですね。
この記事を読んでくれたあなたの「書くこと」が楽しくありますように。
今後も読んで良かった「書くこと」に関する本を紹介していきます。よければまた見にきてください。
それではまた〜。